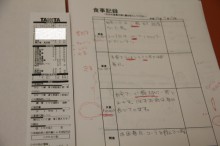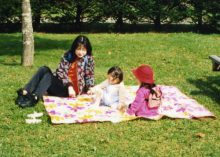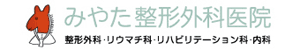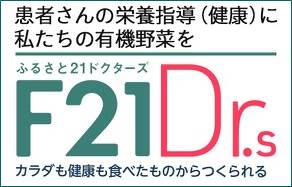みやた整形外科医院内科で、肥満外来を実施しています。
肥満の改善は生活習慣病や整形外科関節痛の治療効果を格段に高めます。そう感じている医療関係者は多いでしょうが、診療で取り組まれている方はほとんどいません。おおかたが「無理」とおっしゃります。
たしかに指導しても減量に成功できるのは5%未満の方と言われています。
当院、内科では。特殊検査などは行わずカウンセリングが主体になります。
肥満は10人いれば10人の理由があります。ただ食事量を抑える様に、体重を減らすように、とアドバイスしても、その通り実施できる方は少ないようです。
方針としては実現可能なライフスタイルの変化を少しずつ提示していくことです。複数の医療機関を受診されている方には治療内容と食の関連性が整合性がとれるようにしなくてはなりません。
体組成や腹囲を測定し、自分の体が何で構成されているかを知り、そして「何を食べてその結果になったのか」をコミュニケーションの中から探し出し、提案します。
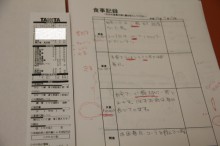
原因はご本人が知っていることも多いのですが、最も誤解が多いのが量を食べなければそれで良い、ということです。
圧倒的に食物繊維が少ない。腸内環境は肥満のメカニズムにも関与しているという事が重要視されています。
食環境を配慮して可能な野菜の食べ方を提案します。特に野菜の種類のこだわりはありませんが、糖質が少ない葉野菜は大事。そして洗っただけでおいしく食べられるトマトやキュウリなど馴染のある野菜を紹介します。
ワーファリン服用の方は野菜をたべてはいけない、とまで誤解している方も。
差し引き、抑制のダイエットは長続きしません。ひとつステップが上昇したら次のステップを踏む。そして減量だけが目的ではなく、いつまでも元気で若々しくいられるために野菜を食べる事を強調し、目標を希望ある項目へ押し上げます。安易な健康食品では幸せは手に入れることはできません。
メソド(手法)よりウエイ(生きる道)、食事療法をそう考えています。ハードルが高いのは言うまでもありません。しかも診療点数が限られているので、どこまで持続できるかが課題ですね。
あれから18年になる。今日は子供の誕生日。
仕事はほとんど休んでいないので、毎日、子どもをどう過ごさせるか、という問題がいつもつきまとっていた。思えば、まあ、よく暮らしていたものだと・・。
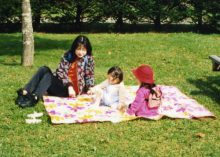
その日の業務が精いっぱい。なんとか学位とか専門医などはこぎつけているものの、出世の切り札、研究論文を重ねる、などということは考えも及ばなかった。
今年の新年祝賀会で14年前にお世話になった県立病院の院長先生と再会できた。
よく辞めなかったね
今日も三食分の家族の食事を準備。外食はほとんどしない。朝5時起き。子供への愛は意識しなくても底力になる。
母というのは出産後の変化であることは間違いないが、日々の暮らしのなかでさらに成長していくもののようだ。だから18年前よりも母としての子供への愛情は深まっているようだし、また、それは人間の成長としての証であるような気がする。

11月にイベントに参加させていただくが、テーマ「うふっやっぱり愛でしょ」とテーマ曲の作詞を今回も担当した。
♪あなたがここに生まれてきたのは、かあさんが貴方を愛していたから♪
関西の愛のパワーも、シニア野菜ソムリエ Noby さんが運んでくる予定。
http://doctor-ls.com/2011/0724/1903/
自分の感情表現を我慢し相手を容認するのも、きちんと叱ってあげるのも愛。
かあさんの愛はなかなか難しい。でもかあさんをしている女性はまだ叱りの状況づくりがうまい。相手の気持ちの逃げ場をつくってあげられる。
さて、そんなこんなで18年、今日、研究費の申請書が手元に。あれっ、かつて出来なかったことが巡ってきたようだ。
人生、思いがけないことばかりだ。
野菜は1つの健康食材ですが、医療で特段取上げられることはありませんでした。しかし食の質によって身体状況がこれだけ変化する、となれば食の中身について医師による研究や議論されて当然であって、これまで農学・薬学系の研究どまりであった食と健康の研究が、人間での検証へと急速に進んできた感があります。
日本人に相応しい食は日本食ですが、その日本食の定義がいまひとつでしたし、低糖質ダイエットを推奨する医師が有名になり、医師が日本の食の未来を先導するどころか食料自給の問題をさらに根深くしてしまうような状況を、私自身、憂いておりました。

ところが医師会講演会での特別講演・杏林大学の教授はその気持ちを払拭させるものでした。カーボン(炭水化物)をおおまかにカウントして、指示された内服・インスリン量にふさわしい食事を選択する(あるいはその逆で応用)、特にこれは外食が多いなどの方に有効となります。もちろん強化インスリン療法を実施している方はカーボンカウントもそれよりは厳密となります。
それは食を良く知ることからはじまります。つまりは食品交換表を良く知らなければはじまらず、古くて新しい食事療法であるのです。と、教授からあらためて講義で教わった感じです。
そして驚愕の事実。低糖質ダイエットを施行した方は動脈硬化が多い、というのは知られていましたが、それが動物性食品だと心疾患、がんなどもはるかにリスクが高くなる、というものなのです。植物性食品グループでは問題なかったようで、つまり血糖値や体重だけ見て「炭水化物をとらなければ肉・魚を沢山たべても大丈夫」としている方々は、かなり危ないということ・・・。容易に推測できることではありますが、やはりエビデンスとして提示されると、強いですね。

教授の講演に先立ち「食事療法に役立つ野菜の基礎知識」と題して前座をつとめさせていただきました。食事療法のスタイルや主義はどうであれ、プランツ(光合成をする植物)を日常の食として大事にしたい、と話しました。それは地球環境にとっても大切な事だと思うのです。
教授講演の後、何か質問は?と指名されましたので、プランツ(植物)を食することの地球環境への配慮、に同意していただきました。(こういった質問をする医師は皆無なので、教授がたじろいだのは言うまでもありませんが、包容力のある方らしく、笑ってかわして下さいましたよ)。
今回の講演会は「患者さまへの愛」を感じました。10人いれば10人の食生活、これまでは「こうあらねばならぬ」の一方通行、「その方の出来ること」からの治療に変化してきたのです。
楽しくなければ続かない!持論です。

そして講演後の懇親会は野菜メニューをふんだんに盛り込んだ内容にしたい、という希望があったので、遠野ふるさと野菜のシニア野菜ソムリエ高橋さんに委ねました。各メニューの野菜料理の提案のほかにサラダバーを特設していただきました。

「食事の前にまずサラダ」が医学の間でも認知されてきていることですからここは重要ポジションなのです。高橋さんには感謝ですし、これからどんどん医学の領域に「良い野菜」を投入していきたい、そのパートナーになっていただきたいと勝手に思っております。


それから株式会社ローヤル様のメキシコ産アボカド。植物性食品は油脂を含めて、なので一価不飽和脂肪酸を含むアボカドはキー食材、日本では生産が稀有なこの脂肪酸を日常食にできることはありがたいのです。
食感が似ているマグロ(こちらは多価不飽和脂肪酸が豊富)は漁獲高は減少しているし水銀の問題がありますしね。しかも代替となるシソエゴマという植物性油脂があるわけですから。
プランツですよ!それは身体と地球環境に優しい「愛ある食材」なんです。
この会を総合的にプロデュースしてくださったのが黒田先生、パッションを感じます。後でご助言をいただきました。「これを食べて元気になろう!が大事だと思います」
そうだ!私が野菜ソムリエを始めるきっかけになったことではありませんか!!
勇気をありがとうございました。