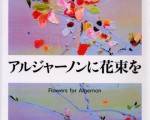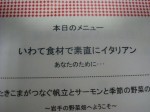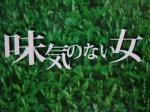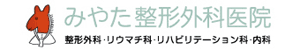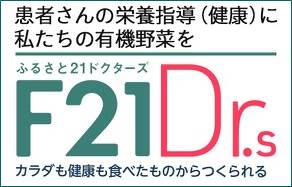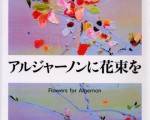
実務とアンチエイジング旅を兼ねて九州へ。飛行機で鹿児島へ向かい、レンタカーで指宿のサツマイモ農家さんを見学。大自然の中で収穫期を迎えたサツマイモが大地にしっかりと根っこむ(注:岩手の方言です)姿はまさに命そのもの。生産者ご夫婦の丁寧な説明と、奥様の蒸したサツマイモが、「鹿児島に来たぞぉ~」と空腹に有難ぁく染み渡る。
その夜は、鹿児島の旅をアレンジしてくださった鹿児島組合食品の部長さんと鹿児島美人方々と芋焼酎で乾杯!初対面なのに懐かしさとか心地よさとか・・・会話の中心はいつもの青果物の事なのだが、鹿児島の方々とイモ焼酎にすっかり癒されてその夜はぐっすりと眠りに。
そして翌日は新幹線で熊本へ。この新幹線、一度は乗る価値あり!略。
熊本の株)果実堂の圃場を見学させて頂く。基礎研究の会社実績とはイメージが異なり、遠くに阿蘇が見えるハウスの土に有機栽培ベビーリーフが育つ。この光景に会社の理念を確認。数年前に自分自身の抱いた「決意あるいは思いつき」を省みて、少しばかり胸が熱くなる。
この旅の間、この文庫本を読む。かなり以前に読み映画でも見た。テレビドラマ化された分は興味が無かったので見ていない。かつての自分とは明らかに解釈が異なり、その頃の自分の未熟さを思い出す。
じっくり自分と向き合えるのがアンチエイジング旅。この旅で沢山の方々と出会い、教えられそして共感、旅をアレンジしお付き合いしてくださった全ての方々に感謝、そうして湧き上がったこころに自分の大切なものを思い出して胸がキュンとなる。
今回のアンチエイジング旅・九州編は希望を維持できそう・・という、メンタルな癒し旅でもありました。九州の「ひと・花・やさい」に心から感謝です。
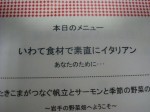


にたきこま収穫際のつもりで準備していましたが、成熟した岩手の食文化を表現したく、会の主旨を少々変更しました。「癒し」もテーマです。
自分で契約栽培(矢巾の藤原さんにお願いしました)して手に入れたにたきこま。メニューにしたりドライトマトにしたり、ペーストにしてみたり。格闘しているうちに、雫石創作農園の方(ペースト)や佐々恵農園さんのドライトマトのテクニックに助けられ、こうして手に入れた食材を使用して今日のメニューに至りました。
これが私の参加者への~あなたのために~という癒しの食です。思いを朝日亭シェフ・勝山氏へ委ねメニューに表現。
素直に・・・は、あまりテクニックを加えずに素材の持ち味で「食して」味わうというものです。二皿目の「海草とグレープフルーツのサラダ」は、特にプロの方が「何、これ?」っていう表情をしていましたが、「先ほどのバーニャカウダなどの残りをさわやかにニュートラルな状態にするため。三皿目の「にたきこま極上パスタ」のパンチを聞かせるためのマイナス・メニューなのです。」と説明にて納得したご様子。
さまざまな領域の方々にお集まりいただきまして、それだけで感動。そして会の間じゅう、意見交換をされる人々の生き生きとした表情に、いわての食の可能性を十分に感じることが出来ました。
翌朝のNHKニュースでさわやかに放映。取材チームの感性が岩手の希望へのメッセージに。
これまで「にたきこま」に関わってくださった全ての方に、心より感謝申し上げます。感動と勇気をありがとうございました。
食を提供する側も癒される・・・幸福感を共有できること・・・癒しの食のコアがここにあります。
最後に、さまざまな注文に文句一つ言わず裏方に徹してくれた県庁流通課の菅原さんに、まごころ込めて「ありがとう」の言葉を。
にたきこま倶楽部 http://doctor-ls.com/tomato/

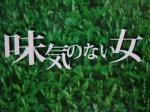
ライフ・ワークでもある味覚のナチュラル・サイエンス。このタイトルでの講義内容依頼でしたので、はりきって講義しました。少々マニアックになってしまうのがたまにキズです。
2時間の講義は3部立て。これまでの食の環境から日本人の体の変化と野菜不足の問題点、その関連を説明。野菜を「おいしいと思って」食べるための味覚の話と、野菜・果物から得られる味覚を、簡単なサイエンスを交えてお話しました。
そのとき放映したDVD「味けのない女」。こちらはかねてから交流させていただいております、果実堂というベビーリーフの有機野菜の施設栽培を行う企業で製作されたものです。創設者は薬学博士の方で、熊本大学との産学連携で、野菜の基礎研究を行うフードサイエンス研究所も兼ね備えています。昨年、岩手の二戸にも工場が出来ました。ホームページ http://kajitsudo.com/
現代の食生活から味覚障害が増えている、その解決のための野菜の役割を解りやすくドラマ仕立てで解説しています。主人公の女性が自分でつんだベビーリーフを食べた瞬間の爽やかな表情がナチュラルで印象的です。
最後は予定外でしたが、「これからも食べていく」という事で、抗加齢医学的な食の選択について説明を追加して合計2時間。
10人の食育対象者いれば10人の食育の語り方。知識を得るだけでなく、アウトプットをどうするかも食育実践には大事です、とお話しさせていただきました。
質問も多く、聴講の方々のレベルの高さが伺えました。なにはともあれ、食育推進アドバイザーという任務の重さを改めて実感しました。研鑽を積んで行きたいと思います。